|
 10月26日(土)に、3回目となるCカード協議会主催「ダイバー自身の安全対策セミナー」が、大阪にて初開催されました。このセミナーは、「ダイバーの安全はダイバー自身が守る」という大原則を改めて見直すと共に、現在起こっている問題点を検証し、今後の対策につなげていこうというもの。今回はおよそ80名が参加し、活発な意見交換も交わされました。当日、参加できなかった方のために、セミナーの模様を紹介します。 10月26日(土)に、3回目となるCカード協議会主催「ダイバー自身の安全対策セミナー」が、大阪にて初開催されました。このセミナーは、「ダイバーの安全はダイバー自身が守る」という大原則を改めて見直すと共に、現在起こっている問題点を検証し、今後の対策につなげていこうというもの。今回はおよそ80名が参加し、活発な意見交換も交わされました。当日、参加できなかった方のために、セミナーの模様を紹介します。
■日にち:2013年10月26日(土)
■会場:大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番36号新大阪トラストタワー 2F
TKP新大阪会議室Room2
■主催:Cカード協議会(実行委員:PADIジャパン)
■協力:海上保安庁 警備救難部救難課マリンレジャー安全推進室
 海上保安庁・警備救難部 救難課/武山晃浩、金川和司 海上保安庁・警備救難部 救難課/武山晃浩、金川和司
まずは昨年1年間のダイビング事故発生状況を、海上保安庁発表の資料を元に、救難課の武山氏が報告しました。
●平成24年のスクーバダイビング中の事故者数は58人であり、過去10年で最多。
●事故者のうち40歳以上の占める割合は67%、死者、行方不明者のうち40歳以上の占める割合は97%。
●経験年数別で見ると、3年以上の経験者が48%を占める。
●事故原因別に見ると不注意や知識技能不足等の自己の過失によるものが55%を占める。
また、先日発表となった2013年1~8月の中間報告も紹介。
●2012年1~8月事故者数42名、うち死者、行方不明者数15名。
●2013年1~8月事故者数27名、うち死者、行方不明者数11名と減少。
●事故者のうち40歳以上の占める割合は81%、死者、行方不明者のうち40歳以上の占める割合は91%
●事故者の約4人に3人は活動頻度が年数回程度以下の者。
同じく海上保安庁・救難課の金川氏からは、「ハインリッヒの法則」の話があり、
●マリンレジャー10万人当たりの死者数を見ると、釣り1.2人、サーフィン、ウインドサーフィン2.8人、ダイビング4.7人
●10万人当たりの交通事故死者数3.5人。ダイビングのほうが死者数が多い!
との発表があり、まとめとしてダイビングは他のレジャーに比しリスクがあることから、ダイビングを提供する事業者は安全確保にしっかりと取り組む必要があり、ダイバーにおいても自分の命は自分で守るとという取り組みが必要であるとの呼び掛けがありました。
 DAN JAPAN/平川雅一 DAN JAPAN/平川雅一
DAN JAPANからは、これまでのデータをもとに、日本とアメリカの事故傾向が比較されました。
■ダイバー数とダイビング事故のまとめ
■日本の死亡者数の推移
■アメリカのダイバー数と死亡者数の推移
■日本の事故、死亡・行方不明の男女による違い
■アメリカの死亡者の男女による違い
■ダイビングにおける死亡の10万人率
■日本とアメリカでの事故原因の違い
■バディの位置に見る問題点
 Cカード協議会(PADIジャパン・トレーニング部) Cカード協議会(PADIジャパン・トレーニング部)
/村上史朗
続いて、過去のダイビング事故の中から3つの事例について、事故の状況や海のコンディション、グループ構成などを詳しく挙げ、「なぜ事故が起こってしまったのか」、「どうして事故を防ぐことができなかったのか」をディスカッション。グループごとに意見交換し、発表するスタイルで行ない、おおいに盛り上がりました。
皆さんも以下の資料(PDF)を見て、考えてみてください。
参加者から
事故事例Ⅰについて
・水面で返事をした、イコール何もくわえていなかった。
・バディの組ませ方に問題。
・バディシステムが機能していなかった。
・そもそも水底集合とはいかがなものか。
・スタッフが多いのに組織編制がなされていなかったのでは?
・オーバーウエイトでは?
・中圧ホースが外れていたのはバディチェックがされていなかったから?
・潜降ラインシステムを完備していれば防げていた。
事故事例Ⅱについて
・1:8の人数比は多すぎ。
・全員ドライで潮流1ノットは泳げない。
・潜降ブイに到着できないのは当たり前。
・この場合でも潜降ラインシステムを工夫すれば安全確保できたはず。
・透視度5mで潜降の指示は無謀。
・このコンディションでは中止もありえたのでは。
・バディシステムが機能していない。
事故事例Ⅲについて
・ダイビング中、チームを離脱させるのはありえない。
・水面での浮力確保は大原則のはず。
・おぼれながら沈んでいく、イコール、オーバーウエイト。
・ウエイトを捨てる、というサバイバルスキルひとつ知っていれば。
・バディシステムが機能していない。 |
Cカード協議会(PADIジャパン・トレーニング部)
/村上史朗
3つの事故事例検証で共通して挙がったのが「バディシステムが機能していない」ということ。改めて「バディシステム」の持つ重要性について確認しました。
バディーシステムとは何か
●自分自身もバックアップシステム
●バディシステムから得られる恩恵
●実態はどうか
●安全の保証であるべき! | 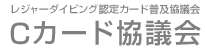
 10月26日(土)に、3回目となるCカード協議会主催「ダイバー自身の安全対策セミナー」が、大阪にて初開催されました。このセミナーは、「ダイバーの安全はダイバー自身が守る」という大原則を改めて見直すと共に、現在起こっている問題点を検証し、今後の対策につなげていこうというもの。今回はおよそ80名が参加し、活発な意見交換も交わされました。当日、参加できなかった方のために、セミナーの模様を紹介します。
10月26日(土)に、3回目となるCカード協議会主催「ダイバー自身の安全対策セミナー」が、大阪にて初開催されました。このセミナーは、「ダイバーの安全はダイバー自身が守る」という大原則を改めて見直すと共に、現在起こっている問題点を検証し、今後の対策につなげていこうというもの。今回はおよそ80名が参加し、活発な意見交換も交わされました。当日、参加できなかった方のために、セミナーの模様を紹介します。
 海上保安庁・警備救難部 救難課/武山晃浩、金川和司
海上保安庁・警備救難部 救難課/武山晃浩、金川和司 DAN JAPAN/平川雅一
DAN JAPAN/平川雅一
 Cカード協議会(PADIジャパン・トレーニング部)
Cカード協議会(PADIジャパン・トレーニング部)