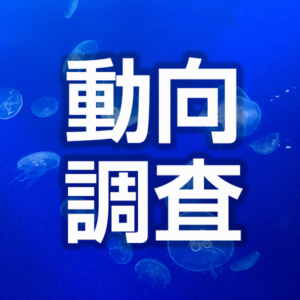Cカードの基礎知識
Cカード(認定カード)についての解説
下記は、一般消費者やダイバーの皆さまより、当協議会に寄せられる質問と回答を記載しています。下記に掲載した説明以外でご不明のことがありましたら、お気軽にお尋ねください。
"「Cカード」という呼び方
「Cカード協議会とは」の項目にも記載していますが、「Cカード」という表現について説明させていただきます。
一般的には「ダイビングライセンス」と言われることもありますが、「ライセンス」という用語からは「免許証」というニュアンスが強く感じられます。Cカードは「免許」とは明確に意味合いが異なるもので、Cカードをそのまま日本語にすると「認定証」という訳になります。国際的に「Certification-Card(Cカード)」と呼ぶのが一般的であることから、日本でも「Cカード」と呼んでいます。
Cカードの意味
Cカードは、レクリエーション・スクーバダイビングに関して「定められた知識と技術(指導基準)」を、ある「特定の時期」に、ある「特定の場所」で、習得したことを証明するものです。ですからCカードは取得した時点から、将来に渡って知識や技術を保証しているものではありません。しばらくダイビングをしていないと、技術(スキル)は低下し、知識も時間と共に忘れてしまうため、前回のダイビングから期間が空いてしまった場合には、以前に習ったスキルや知識を思い出すための「リフレッシュコース(教育機関により名称が異なる)」受講が強く推奨されています。また、Cカードを取得したからといって、どんな地域の、どんな環境でも、自由にダイビングができる能力が身に付いたと言うわけではありません。通常は入門レベル(エントリーレベル)の講習では、以下の範囲内で安全にダイビングするために必要な知識と技術を学びます。
・日中の、比較的穏やかな水域で、バディと共にダイビングする
・深度18mまでの範囲で、なおかつ減圧停止をする必要のない範囲
・頭上に障害物がなく直接水面まで出られる環境
以上の条件の範囲を超える環境では、追加トレーニングが必要となります。また、講習を受けた地域の環境と、大きく異なる環境の地域でダイビングするためには、地域のプロからアドバイスを受けることが必要です。 (例:暖かい南のサンゴ礁の海でCカード取得した人が、初めて冬の北海道の海でダイビングしようとする場合など)
認定基準が持つ意味
ダイバーとなるためには、ある一定の知識と技術が必要と述べましたが、この「ある一定の知識と技術」の内容を定めたものが「認定基準」です。
基準には、ダイバーとして最低限できなければならない技術や、知識として理解しておくべき内容が明確に定められています。この基準によって、エントリーレベル講習の内容が統一され、Cカードを持つダイバーが一定のスキルと知識を習得していることを証明できるのです。また、基準があることによって、ダイバーを受け入れる側は、ダイバー達がこれまでどのような講習を受け、どんな事ができるようになっているのかを知ることが可能となり、どのようなダイビングの受け入れ方をすれば良いのかを判断することができます。言い方を変えれば、認定基準とは、「どのような能力を持った人をダイバーと呼ぶのか」を定義するものです。また、基準には講習をする人(インストラクター)の資格要件や、講習を実施する上で守らなければならない規則なども含まれています。
それぞれの詳しい基準は「採択基準」をご参照ください。
「認定基準の広域性」はユーザーにとって重要
認定基準を決めて実施したとしても、その基準がごく狭い一部の地域でしか使われていなかったり、知られていなかったとしたら、その基準に基づいて発行されたCカードは、ごく狭い地域でしか認知されないことになります。従って、ユーザーにとっては所有するCカードの認定基準が、できるだけ広範囲に普及し、使用されていることが重要となります(Cカードの通用範囲が広さ)。
また、Cカードを発行する教育機関が違っても、同一の最低認定基準が使われていれば、それだけそのCカードが認知される範囲が広がります。Cカードを発行する者は、ユーザーの利便性を向上させるために、自らが使用している認定基準を広める努力をすることが重要であり、Cカードを発行する教育機関の担うべき社会的責任の一つでもあります。
Cカードの国際的有効性と「WRSTCとISO基準」
世界の多くの国や地域で同一の認定基準が使用されていれば、その基準に基づいて発行されているCカードは、同じように「世界の多くの国や地域で通用する」のです。それが「WRSTC最低認定基準」と「ISOダイビング基準」「CMAS基準」です。
当Cカード協議会は、WRSTCの正式加盟組織であり、当協議会加盟社はWRSTC最低指導基準に基づくCカードを発行をしています。そのため当協議会加盟社の発行するCカードは、世界のほとんどで通用するCカードです(2025年現在、WRSTC基準またはISO基準、CMAS基準に準拠していない教育機関もあります)。
ISOは工業分野における最大の標準化機関であり、国際社会で多大な影響を与えています。2007年1月レクリエーショナルダイビングの6基準が承認されました(2025年現在ダイビングに関する項目は40基準)。ISOは157ヵ国が参加する国際的な標準規格を策定するための民間の非営利団体であり、本部はスイスのジュネーブにあります。
WRSTCについて
WRSTCは正式名称を「World Recreational Scuba Training Council」といいます。WRSTC(RSTC)は、1997年1月12日米国フロリダ州オーランドでWRSTC設立に関する最初の会議が開催され、4地域(カナダ/アメリカ/日本/ヨーロッパ)の認定基準管理普及組織の賛同を得て設立された、国際組織です。
WRSTC最低指導基準は、これらの組織及びそれぞれの組織に加盟するCカード発行組織によって採択されており、世界中のほとんどの国や地域に広く普及使用されている基準で、事実上の世界基準となっています(WRSTCのホームページ)。